2025/5/10
昨日結構飲んだので、眠りが浅い。夜に何度か起きて、6時半ごろ起床。
着替えてシャワーを浴び、朝食。

今回の会場は福井大学で、福井駅からは2キロぐらいの距離。今回は観光もしないし、近いので歩いて行くことにする。


駅前の恐竜


途中の福井城址は市役所になっている


ぐるぐるマップに導かれて公園の中を突っ切る


公園の中に「震災記念碑」というのがあった。福井で震災ってあったっけ?と思ったら昭和23年のことらしい。


隣に福井神社がある。一応普通の鳥居もあるのだが、鳥居じゃない門もあるし、なんか普通の神社と違うなあと思ったが、松平家の墓だったのか。


どんどん歩く


8時に福井大学に到着。ぴったり30分歩いた。


会場に入る。トイレに入ったら電気がついていなくて、スイッチもわからないのでスマホの灯りで用を足す。


受付は8:30からなのだが、早めに空いていたので受付。対応しているのはRachelとDanaで、先日の福山でもお世話になった。


今回はOrganizing Committeeに入っていたからか、なんか大きい箱をもらった。中身はパンダのペン立て
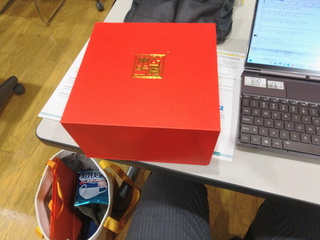

9時から全体会。

ローカルアレンジの川上先生がご挨拶。
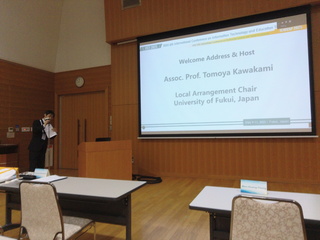
最初のキーノートは東大の山西先生。

Speech Title: Designing Optimal Latent Space toward Knowledge Extrapolation
Prof. Kenji Yamanishi (Tokyo University, Japan)
Speech Time: 09:10-09:50 (May 10, 2025; UTC+9)
情報の埋め込み空間に関するキーノート。
・「埋め込み」について。単語埋め込み、グラフ埋め込みなど。
・latent spaceについて、どのように埋め込むか、どのくらい大きい必要があるか、幾何学的な性質は、等々。
・MDL原理について。(Jorma Rissanenによる)オッカムの剃刀など。MDL原理によるモデル選択。
・埋め込みにMDL原理を適用すると、埋め込みの良さと埋め込み空間の大きさ(次元?)のバランスの良い方法が良いということになる。
・MDLによるモデル選択と同じ方法で、最適な埋込空間次元を推定することができる。
・グラフ埋め込みについて。グラフが木であれば、双曲空間に埋め込むことができる。
・5次元双曲空間にグラフを埋め込むと、200次元のユークリッド空間に埋め込む場合よりも性能が良い。
・双曲空間へのグラフ埋め込みについても、MDLにより最適な次元が推定できる。
・埋め込みに適した空間をどう設計するか。円環状の構造を持つデータは球面、フラットな構造の場合はユークリッド空間、木構造の場合は双曲空間が適している。そこで次元だけでなく空間の種類もMDLで選ぶことができる。
・グラフのデータ拡張について。データを表現するグラフにエッジやノードを追加することでデータを拡張する。このとき、データに適した空間を使うことが重要。データに適した潜在空間でデータをGMMでモデル化し、MDLに基づくサンプリングを行うことでデータ拡張ができる。
・コミュニティ拡張(グラフに対して、既存のグラフの外側にある要素を拡張する)。これは知識の外挿に相当するので難しいタスク。この場合も、グラフを潜在空間に移してからGMMでモデル化し、潜在空間上で既存のクラスタに近くないところに新しいデータを生成する。新しい化学物質の設計などに使うことができる。
MDLによる次元選択がBICより良い、という結果が出ていたので、「MDLとBICってほとんど同じじゃないの?」と質問してみたが、両者が等価なのはデータに対してパラメータ数が十分小さいときだけで、そうでないときには違いがあり、かつMDLの方が良い、という答えだった。
Speech Title: Human-machine communication towards first-person AI
Prof. Akinori Ito (Tohoku University, Japan)
Speech Time: 09:50-10:30 (May 10, 2025; UTC+9)
以前からやっている「一人称AI」に関するトーク。AI alignment に関する質問を受けたが、答えるのが難しかった。
コーヒーブレイクと集合写真撮影。
Speech Title: The New Era of AI Agents
Prof. Wen-Huang Cheng (National Taiwan University, Taiwan)
Speech Time: 11:00-11:40 (May 10, 2025; UTC+9)

・AIエージェントについて。「エージェント」とは環境と相互に作用する知的システム。人間を環境だとしたときにはチャットボットがエージェントとなり、物理世界が環境の場合には自動運転車やロボットがエージェントとなる。
・AIエージェントの歴史。最初の記号的エージェント(DeepBlue)から深層強化学習によるエージェント、Multimodal LLMによるエージェントへ。
・過去にはエージェントはソフトウェアでハードコードされていたが、現状は大規模モデルによる実装になり、将来はAIエージェント自体が自己学習・自己強化するようになる。
・Level 1ではMLLMを使って行動する。Level 2ではMLLMを使って行動の推論(reasoning)をする。そのときには外部ツールを利用する
・Retrieval Augmented Generation (RAG)
・長期記憶、リフレクション、Chain of Thought
・さまざまな推論ベンチマーク
・AIエージェントの応用分野:ゲーム(NPC)
・複数エージェントによる協調、ブレインストーミング
Speech Title: Nurturing Successful Intellectual Styles for Effective Education Technology and Learner Growth
Prof. Li-fang Zhang (The University of Hong Kong, Hong Kong)
Speech Time: 11:40-12:20 (May 10, 2025; UTC+9)

・知的スタイルとは:所有する能力を使う好みの方法、能力をどう使うか
・学生がある特定の問題形式では成績が悪いがプロジェクトはうまくやる、など、似た能力なのに形式によって能力のレベルが違うように見える現象はなぜ起きるのか
・スタイルに関する論争:スタイルの「展性」は生得的か獲得されたものか?
・知的スタイルの3重モデル:価値観依存性、展性、/ TypeI: creativity-generating, II:norm-favoring tendency, III: その他
・知的スタイルに関する研究の違い:文化、ターゲット(生徒、教員)、理論背景、実験形式、教育環境(オンラインかどうか)
・知的スタイルはITの知識とスキルを予測する:多くの研究でType Iのスタイルの人のほうType IIよりが成績が高い
・教育環境(educational climate)が知的スタイルを予測する:深い理解を促すとType Iに、表層的な成績を求めるとType IIになる
・個人属性が知的スタイルを予測する:自己効力感がType Iにつながる
・知的スタイルが取り組みの態度とエンゲージメントを予測する
・知的スタイルがオンラインでの行動を予測する
お昼は生協の食堂(通常営業はしていない)でビュッフェ。


場所を奥の講義棟に移して、午後のセッション。

May 10 (Saturday) 13:30-15:30
Onsite Session 2: AI based Multimodal Data Analysis and Image Processing
Session Chair: Prof. Akinori Ito, Tohoku University, Japan
Generation of Listening Motion of Embodied Conversational Agents Using Speech and Text Information
Akinori Ito, Tohoku University, Japan
3月に終了した伊藤くんの修論の内容。エージェントが相手の話を聞いているときの頭部動作を生成する。VQ-VAEを使っているが、VQのコード割当がイマイチになるので、途中でコード割当をし直すなどの工夫が必要。
Fusion of Region-Constraint Attention and Convolution Neural Network for Blind Image Denoising
Jan-Ray Liao, National Chung Hsing University, Taiwan
画像のデノイジング。通常はCNNのあとにアテンション層をかませるのだが、このモデルではCNNとアテンションを並列にするのと、アテンションにregional constraint maskというのを導入する。単に2つのモデルを並列にするだけでなく、下の画像とモデル出力を掛けたり、2つのモデル出力の積を計算するなど少し凝っている。雑音がある程度以上大きいときに従来法よりもよい。
A DAC using Hierarchical Magic-Square Cell Assignment with Direct Element Modulation to Improve Output Linearity for Signal Processing and Sensor Applications
Yu Takeuchi, Toyama Prefectural University, Japan
イメージセンサ用DAコンバータの線形性を改善する話。さまざまな要因によって素子の線形性が劣化する。2次元に素子を並べて、入力の数値に合わせてその数の素子が導通することで電流を制御するが、2次元に並べた素子上に電流の偏りがあって、それが線形性を下げる。そこで、2次元上の素子の番号を魔法陣として並べて、ONになる素子が2次元上で偏らないようにする。16x16の魔法陣を作るのが大変なので、4x4の魔法陣を4x4の魔法陣状に並べる。
Deep Color Image Quantization Network for Electronic Paper Displays with Color Filter Arrays
Pin-Tzu Huang, National Taiwan Normal University, Taiwan
カラー電子ペーパーのための画像処理。電子ペーパーは白黒なので、色のマスクがあるカラーフィルターをかけることで色を表現する。発色を良くするために、最初に色を強調してからディザリングを行う。U-net構造のディザリングネットワーク(まんなかはViT)と、同じくU-net構造+ViTの再構成ネットワークを使う(なぜ?)。
14:45-15:00
ET7003
Automated Food Image Labeling for E-commerce Websites: Combining Content-Based Image Retrieval and Majority Labeling
Khang Hoang Nguyen, FPT University, Cantho City, Vietnam
料理画像認識で、従来使われているものはベトナム料理が入ってないので新しいデータを作った。手動のラベリングは大変なので、半自動ラベリングをしながら確信度が低いものは手動で再ラベリング・モデル再学習をした。
Time Series-based Electrical Device Classification on Edge with TinyML
Tolga Reis, Galatasaray University, Turkey
Edge AIを志向した電気機器の識別。電源の消費電力の時系列から稼働している機器を推定する。学習はGoogle Colabでやって、エッジではESP32で認識。いくつかのモデルを試し、SimpleRNNが速く、SE-TSNetが最も小さくて精度が高かった。
Domain-Specific Image Captioning: Vietnamese Cuisine on the 30VNFoods Dataset
Huynh Nhu Nguyen Vu, FPT University, Cantho City, Vietnam
さっきのベトナムのお兄ちゃんと同じプロジェクトのようだ。ベトナム料理の画像キャプショニング。データセット20VNFoodsは30種類のベトナム料理画像25000枚ぐらいのデータベース。キャプショニングネットワークの構成は普通(CLIP+FC+MBert Decoder)。
Far Eastern Cultures and the Console User Interface
Antoine BOSSARD, Kanagawa University, Japan
日本語の伝統的な書き方に合わせて、縦書きで右から左に行が流れるコンソール型インタフェースの提案。通常の横書きインタフェースを90度回転させる形で実現する。また、半角数字・記号を全角に変換する必要もある。表示速度は通常表示とほぼ同じ。
コーヒーブレイク。

May 10 (Saturday) 16:00-18:00
Onsite Session 3: Application of Artificial Intelligence in the Education System
Session Chair: Prof. Yuet Hung Cecilia CHAN, City University of Hong Kong, Hong Kong, China
Exploring Language, Society, and Culture with AI Video Creation: A Hands-On Case Study
Yuet Hung Cecilia CHAN, City University of Hong Kong, Hong Kong, China
AI生成ビデオを教育に応用することに関する研究。学部学生にAIビデオ生成の方法を教える2時間のワークショップを行った。そのうえで10分のビデオを作らせて、アンケートを実施。アンケートは36の質問に5段階で答える形式。アンケートの結果の平均値は1.92~2.22に分布していて、項目による違いはあまりない。"Ease of use"や"Perceived usefulness"がやや低い。
C3L: Class-Centric Contrastive Learning for Long-Tailed Learning
Wen-Huang Cheng, National Taiwan University, Taiwan
自動運転のためのAI学習を考えると、まれな状況が多くて、例えば周辺の物体の出現頻度はロングテールになる。そのような稀な物体の出現が事故の元になったりする。
低頻度事象に対処する方法として、オーバーサンプリングやアンダーサンプリングがある。これに対し、C3Lでは画像ドメインとCLIPで変換した潜在空間ベクトルの両方でデータ拡張をする。単なるデータ拡張よりも高性能。
Application and Distribution of Interactive HTML5 Content within Online Courses to Increase Learner Engagement
Malissa Maria Mahmud, Sunway University, Malaysia
やたらエモーショナルな喋り方をする割にはスライドの説明があまりなくてわかりにくい発表。
オンライン学習において学習者のモチベーションを高めるにはどうするか。HTML5でインタラクティブな教材を作った。思想はともかくシステム自体に新しさがあるようには思えない。
A Web-based Answer Platform Implementation for University Course in Flutter Programming Learning Assistant System
Soe Thandar Aung, Okayama University, Japan
FlutterはDart言語によるクロスプラットフォームUIフレームワーク。そのFlutterのプログラミングを学習するクロスプラットフォームの学習システムを作成した。
Node.js、Flutter、Nginxなどを組み合わせてFPLUSシステムを作成した。それぞれのコンポーネントは独立したDockerコンテナに入っていて、それらをDocker Composeを使って連携させている(らしい)。実際にそれで教育したときの学習成果の分析などをやっているが、具体的にどういう内容なのかの説明が不十分でよくわからない。
Are We AI-Ready? Unveiling the Professional Development Needs of Faculty in Higher Education
Wai Kei Wikie Chan, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China
高等教育での教員研修において、AI活用のために何が必要かをアンケート調査。あんまり参考にならなかった。
Balancing AI and Autonomy: The Role of AI in Enhancing Calculus Education
Shiau Foong Wong, Sunway University, Malaysia
数学教育へのAIの活用。学生にChatGPTを紹介した後課題を2つ出して結果を分析。2つの課題に対する学生のセンチメント分析とかやっているのだが課題の内容がわからないのでなんとも言えない。前2つの発表も似たようなテイストだったので、教育系の人は具体的な内容にあまり興味がないのかもなあ。
Effects of an Art-Oriented STEAM Course on Programming Learning Attitudes and Outcomes
Chih-Hung Yu, National Taipei University of Education/Department of Mathematics and Information Education, Taiwan
アート志向のSTEAM教育がプログラミングスキル向上に役立つか。今回試したコースでは、主に2次元の図形描画、回転、極座標などを通じてきれいなパターンを描くことを学ぶ。言語はProcessing。学習態度、成果などを計測し、特に性差について分析。
結果として、時期による差は有意でなかったが、女性の方が男性よりもより不安(anxiety)が高く、楽しさ(playfulness, enjoyment)が低かった。学習成果については性差はない。ディスカッションの中で「授業デザイン自体にジェンダーバイアスがあったのでは?」という質問があったが、答えるのは難しいだろうなあ。
これで会議は終わり。バンケットは駅前なので、バスで駅前に移動。


15分ぐらいで駅前に到着。昨日運営メンバーで飲んだのと同じビルが会場。

ちなみに明日はおろしそばでギネスに挑戦する企画をするらしく、そのための会場設営をしていた。

で、バンケット会場に案内されていったが、お土産屋?

の奥に会議室があって、ここでやるらしい。本当に?こういうのは初めてだ。


最初飲み物がなかったりしてゴタゴタしたが、そのうち飲み物も揃い、適当に飲み食い。福井の観光案内ビデオなど流れる。食べ物は福井名物がたくさん入っていて、厚揚げやおろしそば、ソースかつなど食べた。


ちなみに私は今月19日から台北で開催されるAsian Engineering Deans' Summitに東北大の工学部長として参加する予定なのだが、今回キーノートで喋ったWen-Huang Cheng先生(国立台湾大学)と、Advisory Committeeメンバーとして参加していたWen-Chung Kao先生(国立台湾師範大学)が同会議に参加されるということがわかった。こんなところでそういう人たちに複数会うというのは珍しい。
20時半に終了。

宿に戻り、酔っ払っていて何もできないのでのんびりする。22時過ぎに寝る。
前の日へ 目次へ 次の日へ